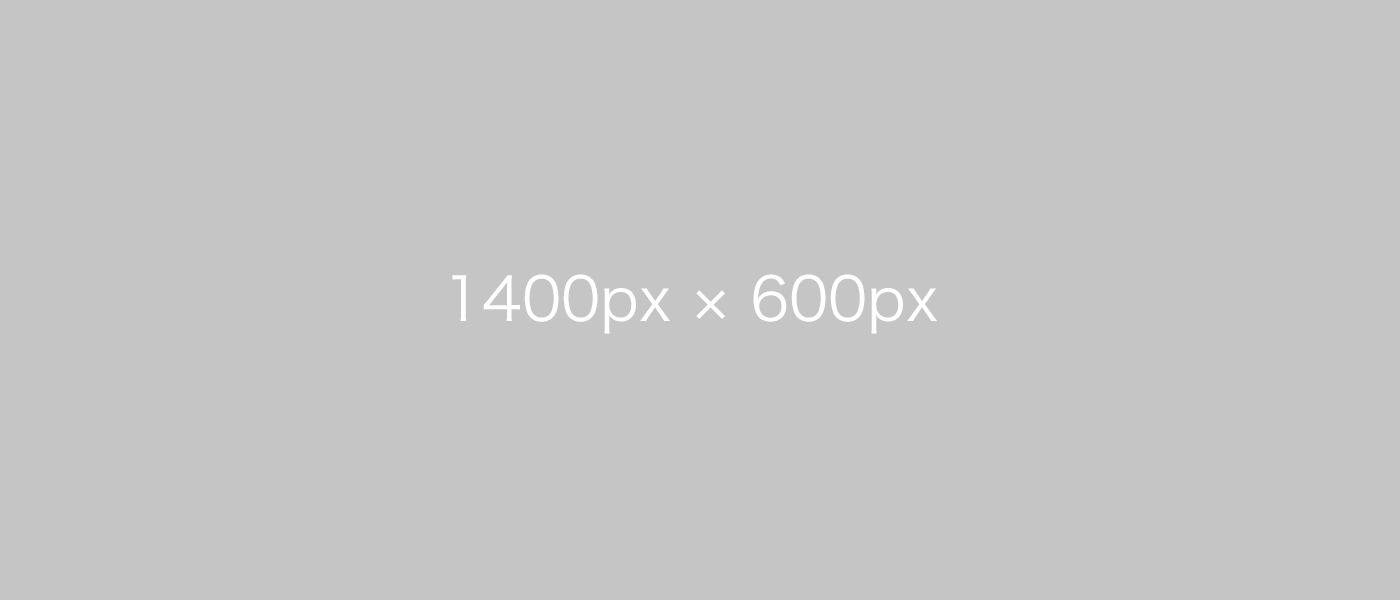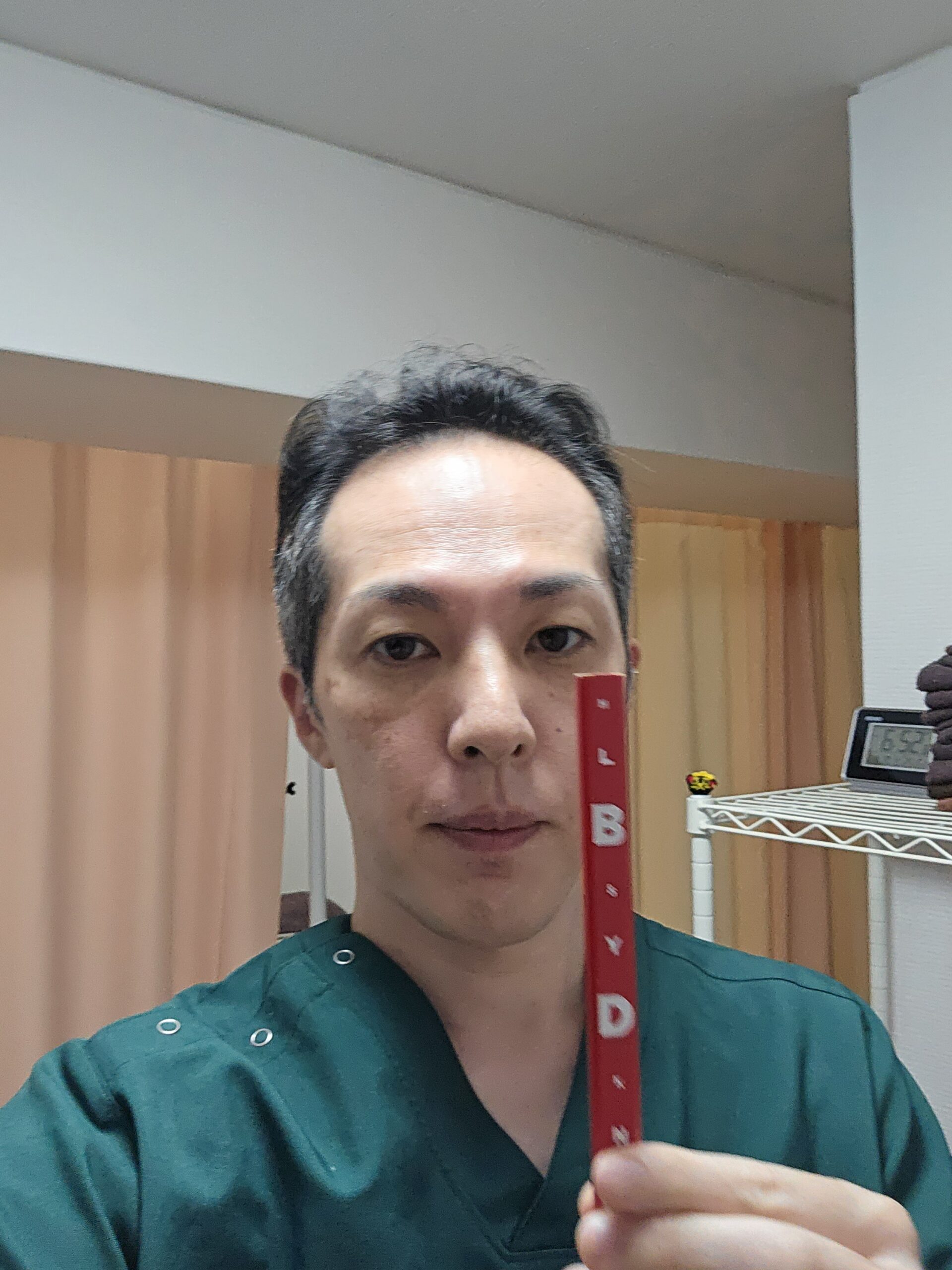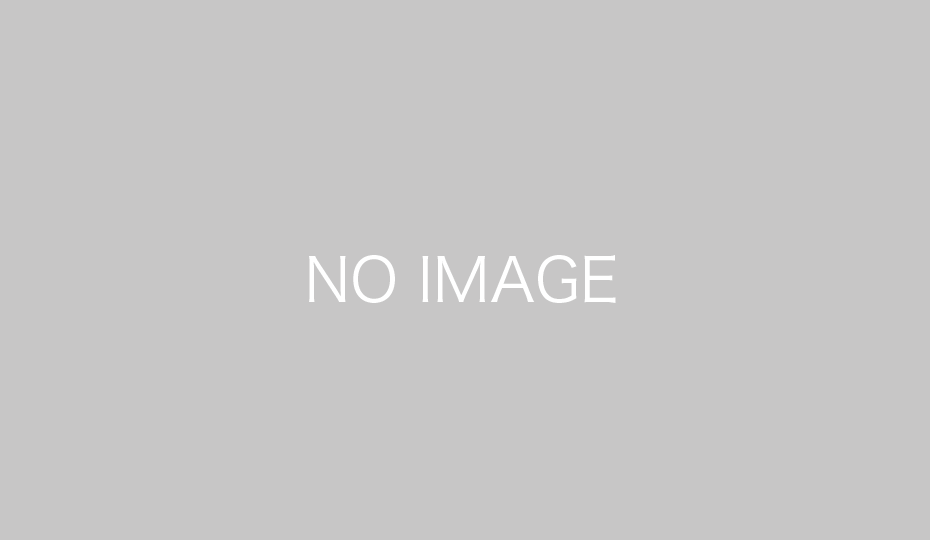前庭動眼反射(VOR)の仕組みをやさしく深掘り:視線がブレない理由と整え方
※この記事は、田口の復習メモも兼ねて「仕組み多め」で解説しています。だれにも読めるようにできるだけ噛み砕いて書いています。
前庭動眼反射(VOR)とは?
VOR(Vestibulo-Ocular Reflex) は「頭が動いても視線を安定させる仕組み」です。歩く・走る・振り向くなど頭部が動いても、景色や文字がブレずに見えるのは VOR が働いているからです。
VORの仕組み(神経経路を中心に)
1. 頭の動きを検出する:前庭器官
- 三半規管:首を振る/頭を傾けるなどの回転運動を検出。
- 卵形嚢・球形嚢:上下・左右・前後の直線加速度を検出。
これらで「どちら向きに/どのくらい」頭が動いたかをミリ秒単位で感知します。
2. 情報の中継と計算:前庭神経 → 脳幹
検出情報は前庭神経を通って脳幹の前庭神経核へ。ここで「視線を安定させるには目をどちらへどれだけ動かすか」を計算します。
3. 目を動かす指令:外眼筋へ
前庭神経核からの出力は、動眼神経・滑車神経・外転神経を介して外眼筋(眼球を動かす6本の筋)へ。たとえば頭を右へ回すと、両眼は同じ角度だけ左へ動いて視界を固定します。
日常での例
- 電車内で揺れていてもスマホの文字が読める。
- ランニング中でも前方の景色を追える。
- 素早く振り向いても視界がビヨンと流れない。
VORが乱れると起こりやすいこと
- めまい・ふらつき・乗り物酔い
- 視界の揺れ(読書やPCで行が飛ぶ/目が疲れやすい)
- 頭痛・首肩こりの慢性化、姿勢の不安定
- 集中力低下、バランス動作の苦手さ
FNT/整体での評価:まず“どこで崩れるか”を見る
- VORチェック:頭部を一定速度で左右/上下へ動かし、視線の安定性や揺れ感を確認。
- 方向差の確認:右回旋は平気だが左で不安定…などの非対称を拾う。
- 関連部位の確認:頸部可動域、後頭下筋群の緊張、視機能(追従眼球運動・サッケード)も併せて評価。
FNTのトレーニング:神経の“入力”を同時に組み合わせる
FNT(ファンクショナル・ニューロ・トレーニング)では単発の刺激よりも、複数の入力を同時に組み合わせるのがポイントです。
- 視線固定 × 頭部運動(VOR練習):ターゲットを一点に置き、頭だけを左右/上下へ動かして視線を固定。
- 呼吸・体幹固定の併用:鼻から吸って長めに吐き、胸郭と骨盤の安定を意識(迷走神経系の調整/姿勢安定の入力)。
- バランス課題を追加:両脚 → 片脚 → 不安定面…と段階的に難易度を上げ、前庭からの入力を増やす。
- 目の運動の組み合わせ:追従眼球運動(パースート)・跳躍性眼球運動(サッかード)を必要に応じて追加。
このように視覚・前庭・固有感覚・呼吸を束ねると、脳幹〜小脳〜大脳運動系の連携が高まり、視界の安定と姿勢制御が同時に整いやすくなります。
後頭下筋群との関係と注意点
後頭下筋群(大後頭直筋・小後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋)は、頭位の微調整と視線安定に関与します。軽い手技で変化が出なければ、その手技で深追いしないことが重要。過剰な圧は防御反応を強め、VORの学習効率を下げることがあります。必要最小限の触刺激+神経課題(VOR/視運動/呼吸/バランス)で“入力の質”を高めます。
自宅でのベース練習(安全範囲で)
- 壁に小さいマークを貼り、顔の正面30〜50cmに設定。
- マークを見たまま、頭をゆっくり左右に10〜15回。視界が揺れない速度から開始。
- 慣れたら上下方向も同様に。違和感があれば即中止してプロに相談。
- 鼻から吸い、口すぼめで長く吐く呼吸を併用。首肩の力みを抜く。
※めまい・吐き気・視界の流れがある時は無理をせず、即ストップ。
まとめ
- VORは「体のブレないカメラ機能」。
- 前庭器官 → 脳幹 → 外眼筋の回路で視線を安定。
- 乱れると、めまい・頭痛・姿勢不安定・目の疲れに直結。
- FNTでは複数入力の同時トレーニングで回路を再学習。
- 手技は最小限・反応優先。変化が乏しければ深追いせず課題を切り替える。
視界の安定は生活の質に直結します。前庭×視覚×姿勢を束ねて整えることで、日常の「見やすさ」「動きやすさ」を取り戻していきましょう。
やさしい整体で、体を本来の動きへ
ぐっすり整体 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、
姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。
スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、
毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。