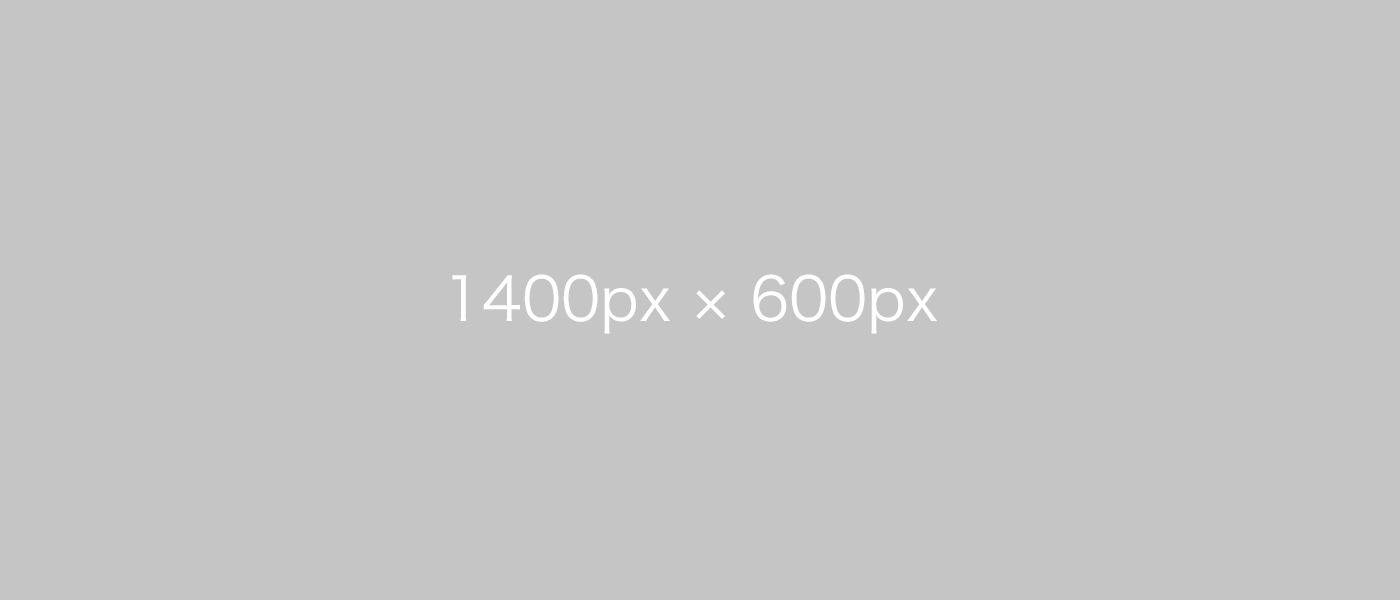後頭下筋群と頭痛の関係
「首の後ろがガチガチに硬い」「目の奥が重い」「後頭部がズーンと痛む」――こういった症状の背景には、後頭下筋群と呼ばれる小さな筋肉が大きく関わっています。
大後頭直筋・小後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋の4つからなる後頭下筋群は、頭と首のつなぎ目にあり、頭の細かい動きを支える重要な存在です。
しかしデスクワークやスマホの使用が続くと、この筋肉群が常に収縮しっぱなしになり、血流低下や神経圧迫を招いて頭痛につながるのです。
頭痛につながるメカニズム
後頭下筋群が緊張すると、後頭部を走る大後頭神経や椎骨動脈が圧迫されやすくなります。
その結果、後頭部やこめかみに広がる神経性の頭痛が生じたり、目の奥の重さ、集中力の低下といった症状につながることもあります。
また、筋膜のつながりから首の硬さが胸郭や腰部へと波及し、全身の疲労感や自律神経の乱れを引き起こすことも少なくありません。
整体でのアプローチ
① 筋緊張の解除(後頭下筋群のリリース)
まずは後頭骨の下に指を添えて、後頭下筋群をやさしくリリースしていきます。
呼吸に合わせて圧を抜きながら、脳が「リラックスしていい」と認識できるように働きかけます。
これにより筋膜の過緊張が解放され、血流が改善し、頭の重さがすっと軽くなることがあります。
② 深層屈筋の活性化(首のインナーマッスルを再教育)
次に「チンノッド」と呼ばれる小さな動きを用いて、頸長筋・頭長筋といった首の深層屈筋を活性化させます。
二重あごを作るようなごく小さな動作で、正しい首の位置を体に再教育していきます。
これにより後頭下筋群の負担が減り、再び緊張しにくい首の状態がつくられていきます。
③ 姿勢全体の調整(胸郭・肩甲帯・骨盤との連動)
首の調整に加えて、胸郭や肩甲骨、骨盤の動きを整えます。
特に肩甲骨周囲の僧帽筋下部や前鋸筋を活性化させると、呼吸が深まり首の緊張が抜けやすくなります。
骨盤の傾きを整えることで背骨全体のカーブが自然に戻り、首が前に突っ込みにくい姿勢が維持されます。
まとめ
後頭下筋群の緊張による頭痛は、首だけの問題にとどまらず、目の疲れや全身の疲労感、自律神経の乱れにもつながります。
整体では「局所のリリース → 正しい動きの再教育 → 姿勢全体の統合」という流れでアプローチすることで、戻りにくく、安定した身体をつくることが可能です。
首や後頭部の痛みでお悩みの方は、一度「神経と筋肉のつながり」に目を向けてみると、新しい解決の糸口が見えてくるかもしれません。
やさしい整体で、体を本来の動きへ
ぐっすり整体 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、
姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。
スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、
毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。