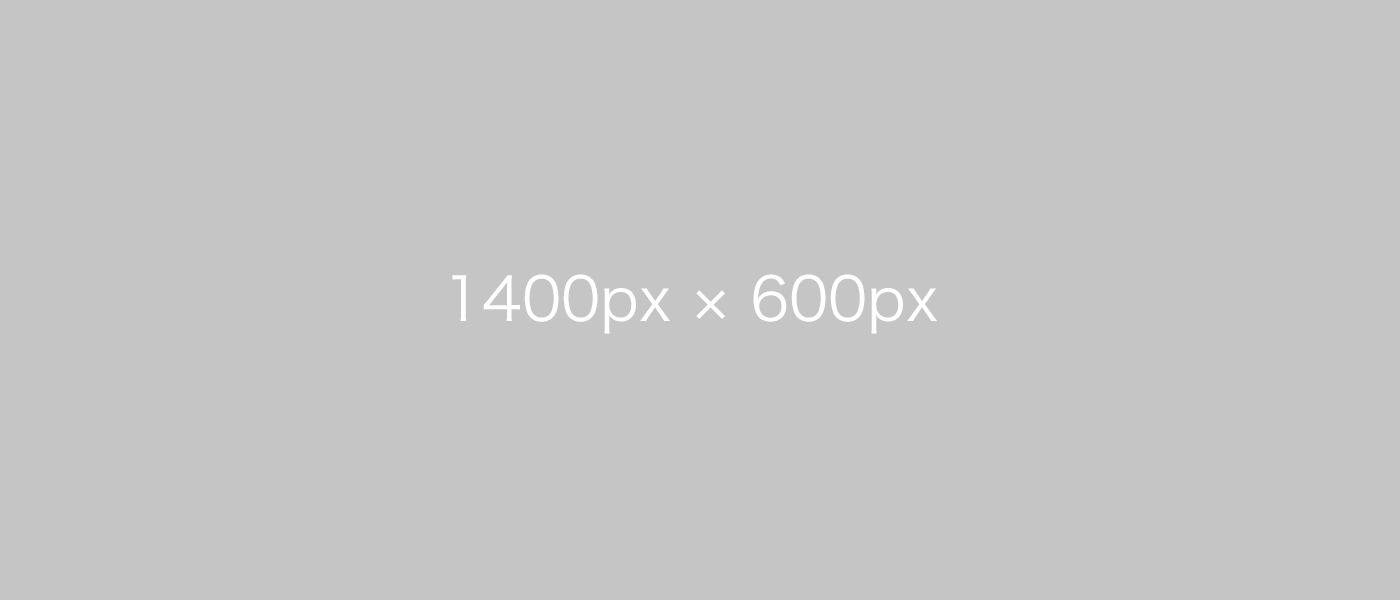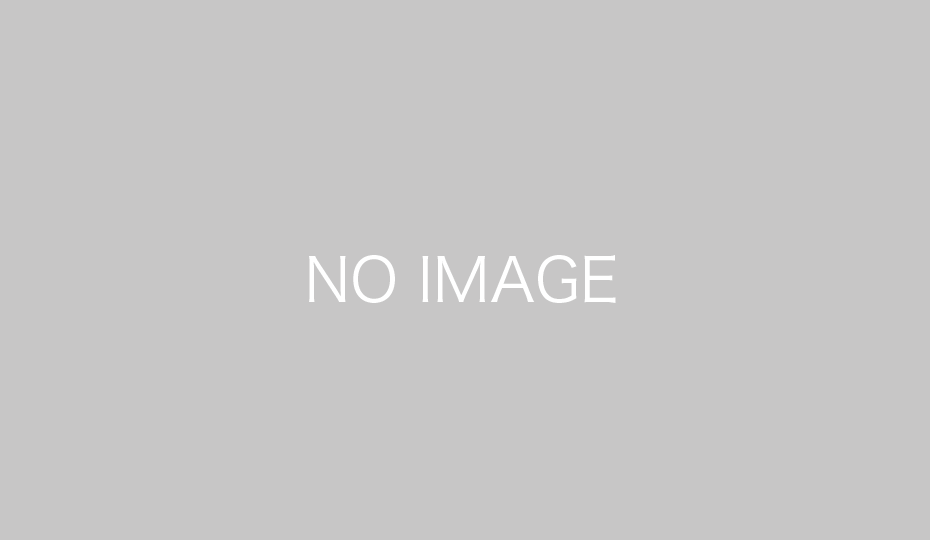今回も後頭下筋群のお話です。昨日と似た感じになのでスルーでも大丈夫です。少し長文になりますが、ぜひ最後まで読んでみてください。
首の付け根の奥にある小さな筋群「後頭下筋群」は、単に頭を動かすだけではなく、姿勢や目の動きの安定に大きな役割を果たしています。特に「頸眼反射(cervico-ocular reflex: COR)」との関係は、デスクワークや長時間の画面作業で起こる首や目の不調を理解するうえで重要です。
首の付け根の奥にある小さな筋群「後頭下筋群」は、単に頭を動かすだけではなく、姿勢や目の動きの安定に大きな役割を果たしています。特に「頸眼反射(cervico-ocular reflex: COR)」との関係は、デスクワークや長時間の画面作業で起こる首や目の不調を理解するうえで重要です。
後頭下筋群とは
後頭下筋群は大後頭直筋・小後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋の4つの筋で構成されます。C1〜C2椎と後頭骨をつなぎ、OA関節(環椎後頭関節)やAA関節(環軸関節)の微細な動きを制御しています。特徴的なのは固有感覚受容器(筋紡錘)の密度が非常に高いことです。つまり「動かす筋肉」というより「感じる筋肉」と言えます。
このセンサー情報は上位頸髄を経由し、前庭系・視覚系と統合されて頸眼反射(COR)に活用されます。
頸眼反射(COR)の仕組み
CORとは、首の筋肉からの固有感覚入力を利用して眼球運動を補正する反射です。たとえば首を右に回すと、CORは視線がずれないように眼球を左に補正的に動かします。これにより、頭や体を動かしても視界が安定し、周囲を正確に認識できるのです。
この反射は前庭眼反射(VOR)と協調して働きます。VORは内耳の前庭器官からの入力で視線を安定させるのに対し、CORは首のセンサーからの入力を使います。両者が協力することで「歩いても視界がブレない」状態を作っています。
デスクワークがCORに与える影響
長時間のデスクワークでは、次のような状態がCORを乱します。
- 前方頭位:頭が前に突き出た姿勢が続くと、後頭下筋群が常に緊張し、センサーが誤作動を起こしやすくなります。
- 画面凝視:モニターを一点に見続けると、眼球運動が制限され、首と目の協調関係が偏ります。
- 浅い呼吸:胸式呼吸や口呼吸が増えると胸鎖乳突筋・斜角筋が過緊張し、深部伸筋(後頭下筋群)とのバランスが崩れます。
その結果、CORが過剰または不十分に働き、視界の安定性が低下します。具体的には「視線を動かすと目が疲れる」「首を動かすと視界が揺れる」「目の奥が重い」といった症状が出やすくなります。
後頭下筋群の過緊張が引き起こす症状
後頭下筋群が硬直すると、次のような一連の問題が連鎖的に起こります。
- 固有感覚入力が歪み、CORが不安定になる。
- 視覚の安定が崩れ、眼精疲労やピント不良が起こる。
- 首の筋肉の防御反射が強まり、肩こり・頭痛が増す。
- TCN(三叉神経頸髄複合体)を介して目や顔の違和感にも波及する。
つまり「目の疲れ」「首の詰まり」「肩の張り」が同時に出る背景には、後頭下筋群とCORの乱れが存在するのです。
整体アプローチ:筋・関節・呼吸から整える
整体施術の目的は、後頭下筋群を「押してほぐす」ことではなく、センサーとしての働きを正常化することにあります。
- OA・AA関節のモビライゼーション:小さなうなずきや回旋運動で、関節の微細な遊びを回復させます。
- 表層筋の鎮静:僧帽筋上部・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋などの過緊張を抑え、深層筋が過剰に働かない環境を作ります。
- 呼吸の再学習:横隔膜と肋骨の動きを促し、首で呼吸を代償しない体の使い方を取り戻します。
- 顎との連携調整:咬筋・側頭筋の過緊張を和らげることで、TCN経由の首への負担を減らします。
FNTのアプローチ:神経系の再教育
FNTでは、首と目の協調を「再教育」するドリルを行います。
- スムーズパースート:目をゆっくり動かし、後頭下筋群のセンサーと同期させます。
- サッカード:素早い視線移動を繰り返し、首の反射応答を高めます。
- VORトレーニング:視標を見ながら頭を小さく動かし、前庭とCORのバランスを整えます。
- 感覚刺激:頬や耳介に軽い触覚刺激を与え、TCNと頸部の過敏を落ち着かせます。
セルフケア:デスクワーク中にできる簡単な工夫
整体やFNTの施術と並行して、ご自宅や職場でできるセルフケアも効果的です。
- ミニうなずき運動:椅子に座り、頭をほんの少しうなずくように前後させる。10回を1セット、首に力を入れずに。
- 視線追従トレーニング:指先を目の前にかざし、ゆっくり左右に動かす。頭は動かさずに目だけで追う。
- 視線+頭の協調:紙に小さなマークを描き、それを見ながら頭を小さく左右に振る。視線はマークに固定。
- 呼吸リセット:1時間に1回は深い鼻呼吸を数回。下肋骨の横広がりを感じると首肩の緊張が和らぎやすい。
- 姿勢リマインド:PC画面は目線の高さに。顎を軽く引くイメージで後頭部を背骨の真上に。
これらは数分ででき、デスクワーク中の首肩・目の疲れを和らげるのに役立ちます。
まとめ
デスクワークが長く続くと、後頭下筋群が緊張し、頸眼反射の精度が落ちていきます。その結果、目の疲れと首肩の不調が同時に現れ、日常生活や仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。
整体では関節・筋肉・呼吸の統合的な調整を、FNTでは神経系の再教育を行うことで、この「首と目の悪循環」を断ち切ることができます。さらに、日常の中でセルフケアを取り入れることで、効果はより持続しやすくなります。
「デスクワークで首も目もつらい」と感じる方は、ぜひ首と目のつながりを意識してケアしてみてください。施術とセルフケアの両輪で、快適な毎日を取り戻すお手伝いをしていきます。
やさしい整体で、体を本来の動きへ
ぐっすり整体 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、
姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。
スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、
毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。