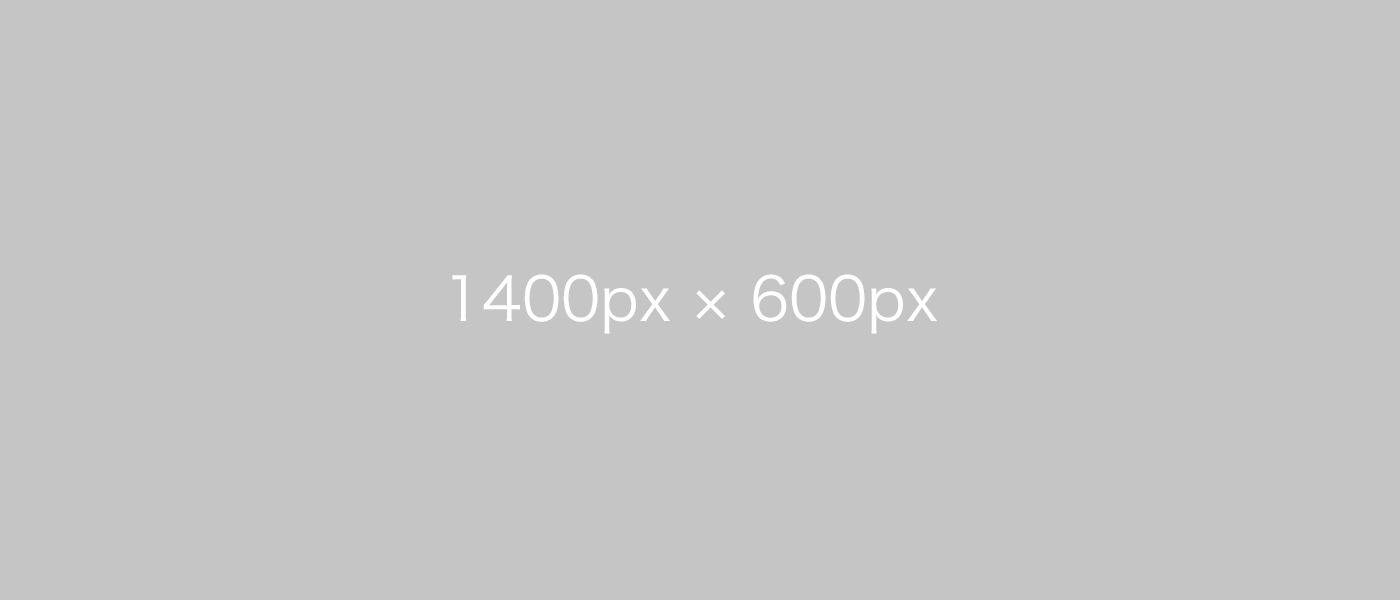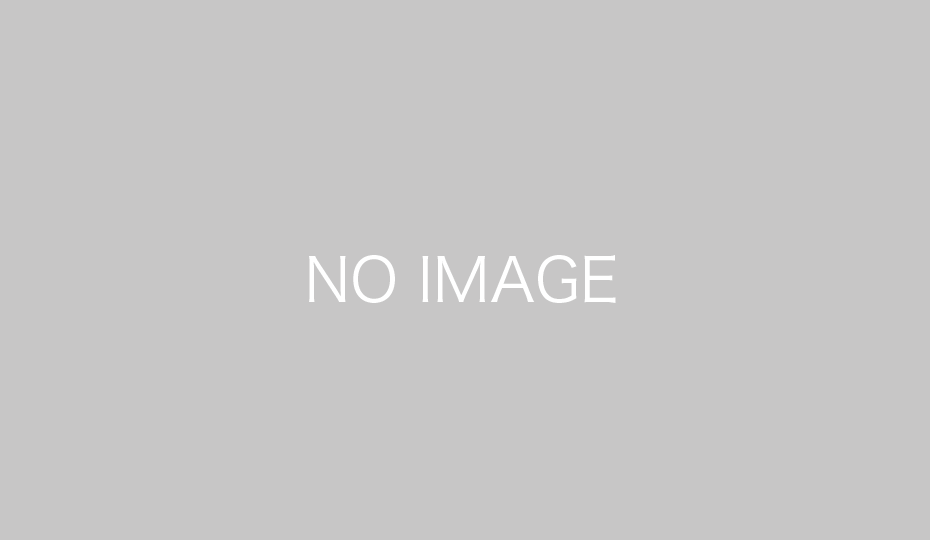夜になってもなかなか眠れない、やっと寝ても夜中に何度も目が覚める、朝早くに目が覚めてそのまま眠れない。
このような「不眠」の悩みは、ただの“寝不足”では済まされず、「集中力や記憶力の低下」「気分の落ち込み」「自律神経の乱れ」など、日常生活全体に影響を及ぼします。
「眠れないのは年齢のせいだから」「ストレスがあるのは仕方ない」と思っていませんか?
実は、不眠の多くは「脳と神経が本来の働きを発揮できていない」という“機能のズレ”から生じていることが多く、ここを整えることで変化が起きるケースがたくさんあるのです。
不眠とは

「不眠症」とは、十分な睡眠環境があるにもかかわらず、満足のいく眠りが得られず、日中の生活に支障が出る状態を指します。主なタイプは次の通りです:
・「入眠困難」:なかなか寝つけない
・「中途覚醒」:夜中に何度も目が覚める
・「早朝覚醒」:朝早くに目が覚めて再び眠れない
・「熟眠障害」:眠っても疲れが取れない
原因は一つではなく、「自律神経のバランス」「ホルモン分泌」「神経系の情報処理」「生活習慣や環境」など、複数の要因が関わっています。その中でも、神経系の機能に着目すると「なぜ眠れないのか」の本質が見えてきます。
🚨 レッドフラッグ(注意が必要な不眠)

不眠の多くは生活習慣や神経機能のズレなどから起こりますが、中には「命に関わる疾患や重大な病気のサイン」として現れているケースもあります。以下のような症状を伴う場合は、自己判断せず、できるだけ早く医療機関を受診してください。
・「眠れない」と同時に、強い抑うつ感や自殺念慮がある
・急激な体重減少や発熱、全身倦怠感が続く
・睡眠中に大きないびきと無呼吸が繰り返される(睡眠時無呼吸症候群の可能性)
・眠気が日中に極端に強く、会話中や運転中に寝てしまう(ナルコレプシーなどの可能性)
・幻覚や妄想、極端な情動変化を伴う
こうした場合は、整体やセルフケアだけで対応するのではなく、まず医療機関で原因を確認することがとても大切です。その上で、必要に応じて体や神経のケアを併用していきましょう。
生活習慣の影響

私たちの睡眠は、体内時計を司る「視床下部の視交叉上核」を中心に、自律神経やホルモンのリズムによってコントロールされています。
しかし、現代の生活はこのリズムを乱しやすい要素がたくさんあります。
夜遅くまでスマホやパソコンのブルーライトを浴びることで「メラトニンの分泌が抑えられ」、寝つきが悪くなったり、昼夜逆転の生活が続くことで「自律神経のリズムが崩れたり」します。カフェインの摂りすぎや就寝前の飲酒、運動不足、ストレスの蓄積なども、眠りの質を下げる原因です。
また、呼吸が浅くなっていたり、姿勢が悪くなっていたりするだけでも、自律神経のバランスは崩れやすくなり、「休息モード(副交感神経)」への切り替えができにくい体になります。
ここで大切なのは、「生活習慣の見直しが不眠改善の大前提」であるということです。
実際にご来店される方の中には、「眠れるようにしてくれ」と完全に他人任せの気持ちで来られる方もいます。しかし、そのような方は残念ながら良い変化が出にくいのが現実です。「生活習慣を見直し、自分自身の行動を変えていくこと」、そしてそれに加えて「体の状態を整えていくこと」の両方が揃って初めて、神経が本来の働きを取り戻していきます。
生活リズムや環境への意識と、体のケアをセットで考えることが、眠れる体への第一歩です。
一般的な治療法

不眠への一般的な対応としては、まず「医療機関での診察」がとても重要です。原因が内科的・精神科的な疾患や薬の副作用などによる場合もあるため、まずは医師による検査や評価を受け、命に関わる要因や治療が必要な病気がないかを確認することが第一歩となります。
診察の結果、器質的な問題がない場合や、生活習慣の乱れが主な原因と考えられる場合には、次のような治療法が行われます。
・「薬物療法」:睡眠薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾ系など)が用いられることが多く、短期的には効果がある場合があります。ただし、依存や耐性のリスクがあり、根本的な原因を解決するものではありません。
・「睡眠衛生指導」:就寝前のスマホ・カフェインを控える、一定の時間に起きる、寝室環境を整えるなどの生活習慣改善が中心です。
・「認知行動療法(CBT-I)」:睡眠に対する考え方や習慣を見直し、行動を変えていく心理的アプローチです。近年は薬に頼らず睡眠改善を目指す方法として注目されています。
これらはどれも重要な手段ですが、「なぜ脳が眠れない状態になっているのか」という根本の“神経的な原因”にまでは届かないことが多く、生活習慣の見直しや薬の使用だけで改善しないケースも少なくありません。
そのような場合には、体や神経機能そのものへのアプローチを組み合わせることで、改善の可能性が大きく広がります。
整体は“プラスアルファ” 整体だけでは難しい理由

整体によって体を整えることで、「自律神経のバランスを整えたり、呼吸や血流を改善したり」することは可能です。
姿勢や筋肉の緊張が和らぐことで、睡眠の質が上がる方も多くいらっしゃいます。
しかし、実は整体だけでは「眠れない脳」を直接的に変えることは難しいのです。
なぜなら、不眠の根本には「脳と神経が切り替えられない状態」があり、これは筋肉や関節だけを整えても解決できません。整体は大切な土台になりますが、「神経システムそのものへのアプローチ」が必要です。
FNT(ファンクショナル・ニューロ・トレーニング)によるアプローチ

ここで重要になるのが、「FNT(ファンクショナル・ニューロ・トレーニング)」という神経機能に着目したアプローチです。
FNTでは、「眠れない脳」がなぜ切り替えられないのかを、神経の働きそのものから探っていきます。
例えば、「脳幹(PMRF)」は自律神経の出力や姿勢筋のトーンを調整する重要な中枢であり、交感神経と副交感神経のバランスにも深く関わります。ここが過剰に興奮していると、「戦う・緊張するモード」が続き、体が休息モードに入れません。FNTでは「眼球運動(スムーズパースート・VOR)」や「頭部刺激」「体性感覚入力」などを通じてこの領域の機能を調整し、「切り替える力」を取り戻していきます。
また、「小脳や前庭系」も睡眠と深く関係しています。小脳は姿勢や運動だけでなく、自律神経の反応性や情動にも影響を与えます。これらの領域を適切に刺激することで、「落ち着く」「安心する」という神経の出力がしやすくなり、自然な眠りへと導かれます。
FNTは、単なるリラックスではなく、「眠れる神経システム」へと再教育していくアプローチです。これは薬でも整体だけでも届かない領域であり、不眠を根本から整える鍵となります。
諦めないで
「もう何年も眠れない」「薬をやめられない」と諦めてしまっている方も少なくありません。しかし、「神経は一生を通じて変化し続ける力」を持っています。
情報処理や自律神経の切り替えは、適切な刺激を与えることで再び働きを取り戻すことができます。
眠れないのは「あなたが悪い」からではなく、「脳と神経が今はうまく切り替えられなくなっているだけ」かもしれません。そこに可能性がある限り、「眠れる体へと再構築する道」は必ずあります。
まとめ:生活習慣と体を整えることが、眠れる脳をつくる第一歩

不眠は、「生活習慣」や「環境」「ストレス」、そして「神経の情報処理のズレ」が複雑に関わって起こります。
「眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「熟睡できない」といった不眠症状は、薬や生活改善だけではなかなか改善しないこともありますが、「体と神経の両面から整える」ことで、再び“眠れる力”を引き出せる可能性があります。
FNT(ファンクショナル・ニューロ・トレーニング)による神経へのアプローチは、自律神経や脳幹・小脳の働きを整え、「眠れる神経システム」へと再教育していく根本的な方法です。これに加えて、日々の生活リズムや行動を見直すことが、自然な眠りへの道を開きます。
仕事やプライベートなどの「生活習慣を変える」というのは確かに簡単なことではありません。しかし、そこにこそ“眠れる力”を取り戻す大きなチャンスがあります。小さな一歩からで構いません。眠れない夜を変えるために、自分の神経と体を見つめ直す一歩を踏み出してみてください。
「たぐち整体 ぐっすり 福岡天神院」では、FNTを用いた神経の再教育と整体による体のケアを組み合わせて、あなたの“眠れる体”づくりをサポートしています。
眠れない夜や慢性的な不眠でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの体に本来備わっている「ぐっすり眠る力」を、一緒に引き出していきましょう。
やさしい整体で、体を本来の動きへ
たぐち整体 ぐっすり 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、
姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。
スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調・自律神経系の不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、
毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。